「勉強も運動も、全然やる気がなくて…」
「何を言っても返事だけ。全然動かないんです」
そんなふうに感じること、ありませんか?
もしかすると、
「私の関わり方が悪いのかな」
「ちゃんと育てられてないのかも…」
と、自分を責めてしまうママ・パパもいるかもしれません。
でも結論から言うと――
やる気が出ないのは“親のせい”ではありません。
そして、子ども自身の“性格”のせいでもありません。
そこには、脳の仕組みと発達段階に基づいた“ごく自然な理由”があるのです。
子どもの脳は“やる気”を出す準備中

実は、子どもが「やる気」を出せるようになるのは、脳のある部分が発達してから。
その場所とは、前頭前野(ぜんとうぜんや)。
ここは「意志力」「集中力」「判断力」など、人間らしい高度な思考を担う部分ですが、発達が完了するのはなんと20歳前後とも言われています。
つまり、子どもはまだ“やる気をコントロールする脳”が未完成なんです。
大人のように「先を見通して努力する」「気分を切り替えてやる気を出す」というのは、そもそも難しい時期なんですね。
「やる気がない」のではなく、「出し方を知らない」

ここで大切なのが視点の転換。
やる気がないのではなく、
やる気の“スイッチの押し方”がまだわからないだけ。
私たち大人も、たとえば…
- 朝から元気に動ける日と、そうじゃない日がある
- 誰かに「今日すごいね!」って言われるとやる気が出る
- 逆にプレッシャーをかけられるとやる気が下がる
…という経験、ありますよね。
子どもも同じです。
むしろ、もっと影響を受けやすいぶん、環境・声かけ・身体の状態で「やる気」は大きく変わるのです。
“脳が動き出す声かけ”はこれ!
じゃあ、どう声をかけたらいいの?
ここで効果的なのは、「評価」ではなく「共感+問いかけ」。
たとえば、
×「なんでやらないの?」
→ 脳は“防御モード”に入り、やる気ダウン
〇「今日はなんか気が乗らない日かな?」
→ 感情に寄り添うことで、前頭前野が少しずつ働き出す
〇「どこまでだったらやってみようか?」
→ 自分で“選ぶ”ことがやる気を引き出す
こうした声かけは、親子の信頼関係と子どもの自己決定感を育てる一歩になります。
身体を動かすと“やる気のエンジン”がかかる

さらに、もう一つ大事なアプローチが【運動】。
実は、体を動かすと脳にドーパミン(やる気ホルモン)が出て、モチベーションが自然に湧きやすくなるのです。
だから、
「勉強の前に少し体を動かす」
「ジムで運動してから宿題に取り組む」
といったルーティンは、脳のエンジンを“自然に”かける効果的な方法です。
自分で動ける子になるために──親ができること

やる気を外から押しつけるのではなく、
内側から引き出せる子に育ってほしい。
そのために親ができることはたった一つ。
“動き出した瞬間”を見逃さずに認めること。
「今、自分から動いたね」
「それ、昨日より進んでるよ」
「ちゃんと見てたよ」
この声かけがあるだけで、子どもの脳は“次もやろう”と自動的に動き出すのです。
最後に:やる気は「教えるもの」じゃない。「育つ環境」が大事。
「やる気がないのはダメ」ではなく、
「やる気を育てる場所を、どうつくるか?」が大切です。
子どものやる気は、“褒める”“叱る”で変わるのではなく、
「自分でやれた」と思える成功体験と、「それを認めてもらえた」という安心感で育ちます。
だから、保護者が自分を責める必要はありません。
今日から少しずつ、「育つ土壌」を一緒につくっていきましょう!


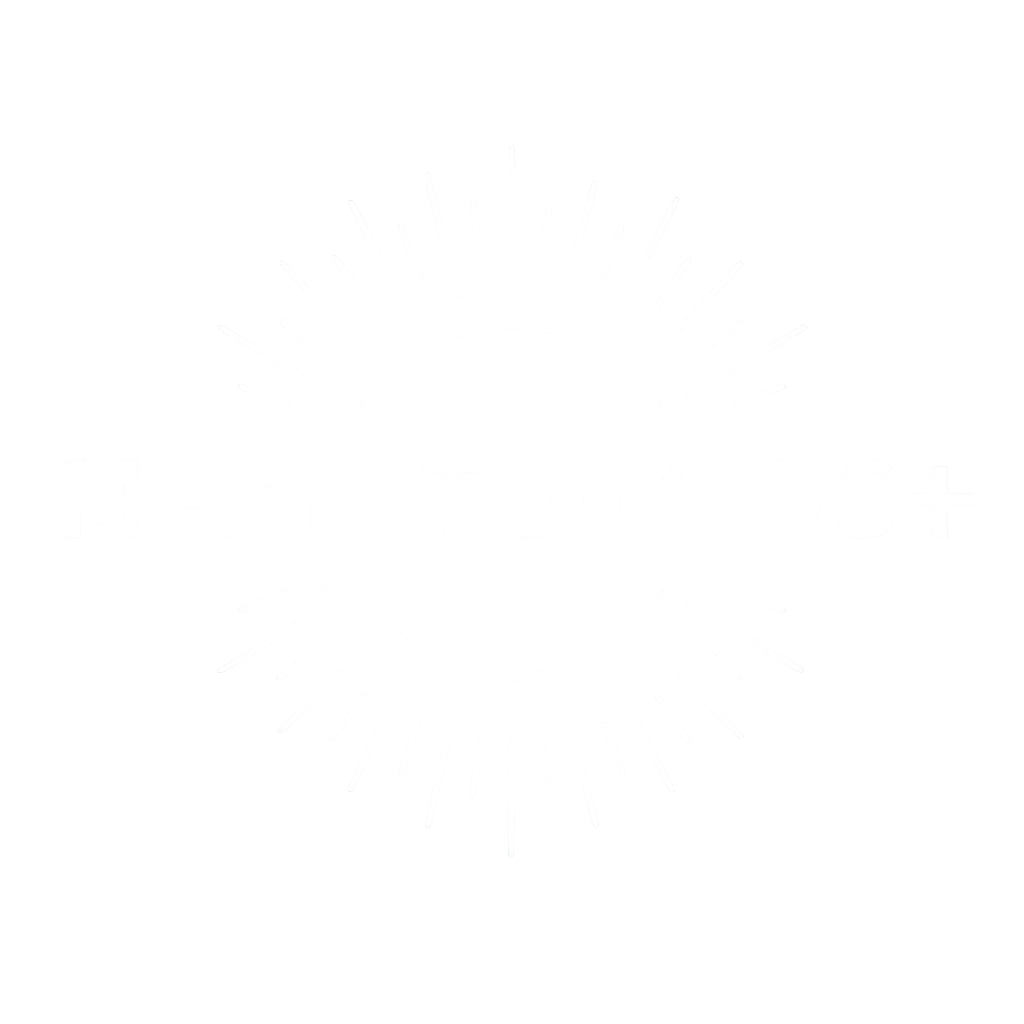










_白抜き-1024x576.png)