~体を動かすことで脳も育つ、その理由とは~
「うちの子、机に向かってる時間は長いのに、集中できていない気がする…」
「勉強が苦手な子は、やっぱり運動より学習塾が必要?」
実は、子どもの“学びの力”を伸ばしたいとき、
運動がとても大きな鍵になるって、知っていましたか?
今日は、「運動と学びの意外な関係」について、科学的な視点と現場の体験をもとに解説していきます!
子どもの脳は、「動きながら」育っていく

最新の脳科学では、
「体を動かすこと」と「脳の発達」は、切っても切れない関係にあることが分かっています。
特に関係しているのが「海馬」と「前頭前野」という2つの領域。
これは記憶力・注意力・感情のコントロールなど、“学習に直結する力”を担う脳の中枢です。
そしてこれらの領域は、単に机で勉強しているだけでは活性化されません。
むしろ――
ジャンプ、スキップ、バランス、手足の連動などの“動き”が刺激になって、どんどん育つのです。
運動する子は「考える力」も育ちやすい?
ある研究では、週3回以上の運動習慣がある子どもは、
・注意力
・問題解決能力
・作業記憶(短期記憶)
などが有意に高い傾向があることが示されています。
つまり、「動くこと」は、ただの体力づくりではなく、
“頭のよさ”にもつながるトレーニングなのです。
「学習力」と「身体操作力」はリンクしている!

特に小学生低学年~中学年くらいの子どもには、
✔ 手先が不器用
✔ 姿勢が保てない
✔ 体の左右バランスが悪い
という“身体面の課題”が、学習に影響しているケースがとても多く見られます。
たとえば――
🧠 姿勢を保つ → 集中力が持続する
椅子にまっすぐ座っていられるには、体幹や背中の筋力が必要。
姿勢が崩れると、呼吸も浅くなり、思考もまとまりにくくなります。
🧠 書く動作 → 運動神経と手先のコントロール
字が汚い・ノートがうまく取れない子は、運動面の課題(視覚と手の連動、上半身の安定性など)を抱えていることも。
🧠 空間認知 → 算数や図形理解に関係
体を使って空間を把握する力が育つと、図形問題や構造的な理解にもつながりやすいのです。
トレーニングで「学びの下地」をつくる
当ジムでは、子どもの身体能力を伸ばすことはもちろん、
“学ぶ力の土台”も整えることを目指したトレーニングを提供しています。
✅ ラダーやジャンプトレーニングで「注意の切り替え」
→ スピード感ある指示に反応しながら動くことで、
情報処理力や集中の切り替えが磨かれます。
✅ バランス&体幹トレーニングで「姿勢力」
→ 長時間座ってもブレない軸をつくることで、学習時の集中力がアップ!
✅ 左右の手足を交差する動きで「脳の連動強化」
→ クロス運動は、左右の脳をつなげるといわれ、記憶力や発想力に好影響。
勉強が苦手な子ほど、「運動」で変われる

「勉強ができない子」は「頭が悪い」わけではありません。
多くの子は、“学びやすい体”が整っていないだけ。
この「体の使い方」と「学びやすさ」をリンクさせてあげることで、
✔ 集中しやすくなる
✔ 話を最後まで聞ける
✔ 自信を持って取り組める
という、勉強に向かう“姿勢”そのものが変わってくるのです。
最後に:「学びの力」は、動くことから始まる
子どもたちは、頭だけで育つわけではありません。
体と心と脳が、ひとつのユニットとして発達していくのが、子ども期の特徴です。
だからこそ――
「勉強が苦手そう」「落ち着きがない」「自信がなさそう」
そんなときは、“体を動かす場所”を増やしてあげてください。
動きの中で、子どもは自分のリズムを見つけて、
やがて“学びやすい子”へと変わっていきます。
それが、私たちがこのジムで目指している姿です。


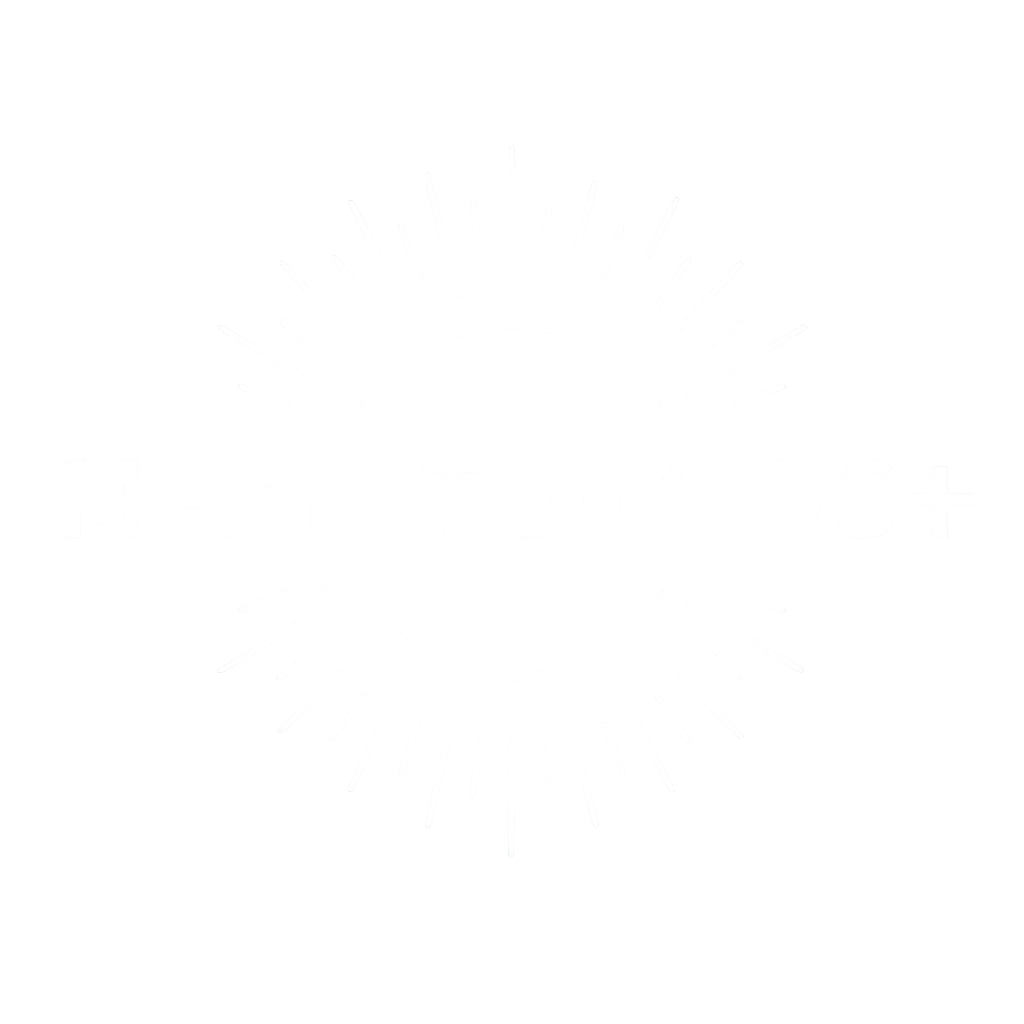










_白抜き-1024x576.png)