「非認知能力って最近よく聞くけど、結局なんなの?」
「勉強と関係あるの?」
「スポーツに関係あるの?」
保護者の方から、そんな疑問をいただくことが増えました。
これまでの教育は「認知能力=テストで測れる学力」が中心でしたが、
今、世界中で注目されているのが、「非認知能力」。
簡単に言えば、
“数値化できないけれど、人生を大きく左右する力”です。
そしてこの非認知能力――実は「スポーツ」や「運動」を通して育てることができるんです。
非認知能力って、具体的にどんな力?

たとえばこんな力が、非認知能力に含まれます:
- 自己肯定感(自分を信じる力)
- 自己効力感(やればできるという感覚)
- レジリエンス(失敗から立ち直る力)
- 協調性、共感力
- 自己コントロール(感情や行動を整える力)
- 意欲、粘り強さ、計画力
これらは、どれも社会に出てから必要な力ばかり。
そして驚くことに、学力の伸びや将来の年収、幸福感にも強く関係すると言われています。
なぜ今、非認知能力がこんなに注目されているの?
きっかけは、2015年にOECD(経済協力開発機構)が発表した教育方針。
そこでは、
「これからの社会に必要なのは、知識よりも“生きる力”である」
という強いメッセージが打ち出されました。
日本でも文部科学省が非認知能力を重視する方針にシフトし、
多くの教育現場や保護者が「テストでは測れない力」に注目しはじめています。
スポーツは“非認知能力のトレーニングジム”

じゃあ、どうやってこの力を育てるの?
答えは意外とシンプル。「身体を動かすこと」です。
運動・スポーツの場には、非認知能力を伸ばす要素がぎゅっと詰まっています。
たとえば…
- 失敗してもあきらめずにトライする → レジリエンス
- コーチの指示を聞いて行動する → 自己コントロール力
- チームで協力して目標を目指す → 協調性・共感力
- できた瞬間の“やった!”という感情 → 自己効力感
これらは全て、教科書では身につけられない「生きる力」。
だからこそ、運動やスポーツは“動く教科書”とも言えるのです。
パーソナルトレーニングなら、“もっと深く”育てられる

子ども向けのパーソナルトレーニングでは、
「一人ひとりの心の状態」に合わせて、
適切な声かけ・難易度設定・振り返りを組み合わせることができます。
たとえば、
ある子どもができなかったトレーニングを自分で考えて乗り越えたとき、
「今、自分で方法変えたんだね!それが“考える力”だよ」
「失敗しても続けたこと、すごく価値があるよ」
こうした言葉でフィードフォワードすると、
子どもは自分の“内側の力”に気づきます。
これは、単に体を鍛えるだけの運動指導では得られない、大きな価値です。
「スポーツ=非認知能力を育てる場所」としてのジム

私たちのジムでは、「体力」や「技術」を育てるだけでなく、
子どもが“自分を信じて前に進む力”を育てることを何より大切にしています。
成績や結果ではなく、
✔ どれだけ失敗してもまたチャレンジする姿
✔ 昨日より1歩だけ前に進んだその瞬間
✔ 他の子の成功を素直に喜べる心
そういった“人としての成長”こそ、最大のトレーニング成果だと考えています。
最後に:今こそ「目に見えない力」を育てるとき
非認知能力は、目に見えません。
でも、確実に子どもの“これから”を支える土台になります。
テストでは測れないけれど、
生きていく上で何よりも必要な力。
そして、それを最も自然に育てられるのが、
体を動かすという行為そのものなんです。
だからこそ、
「スポーツ=競技力」ではなく、
「スポーツ=人生を育てる時間」として捉える保護者が増えてきているのです。


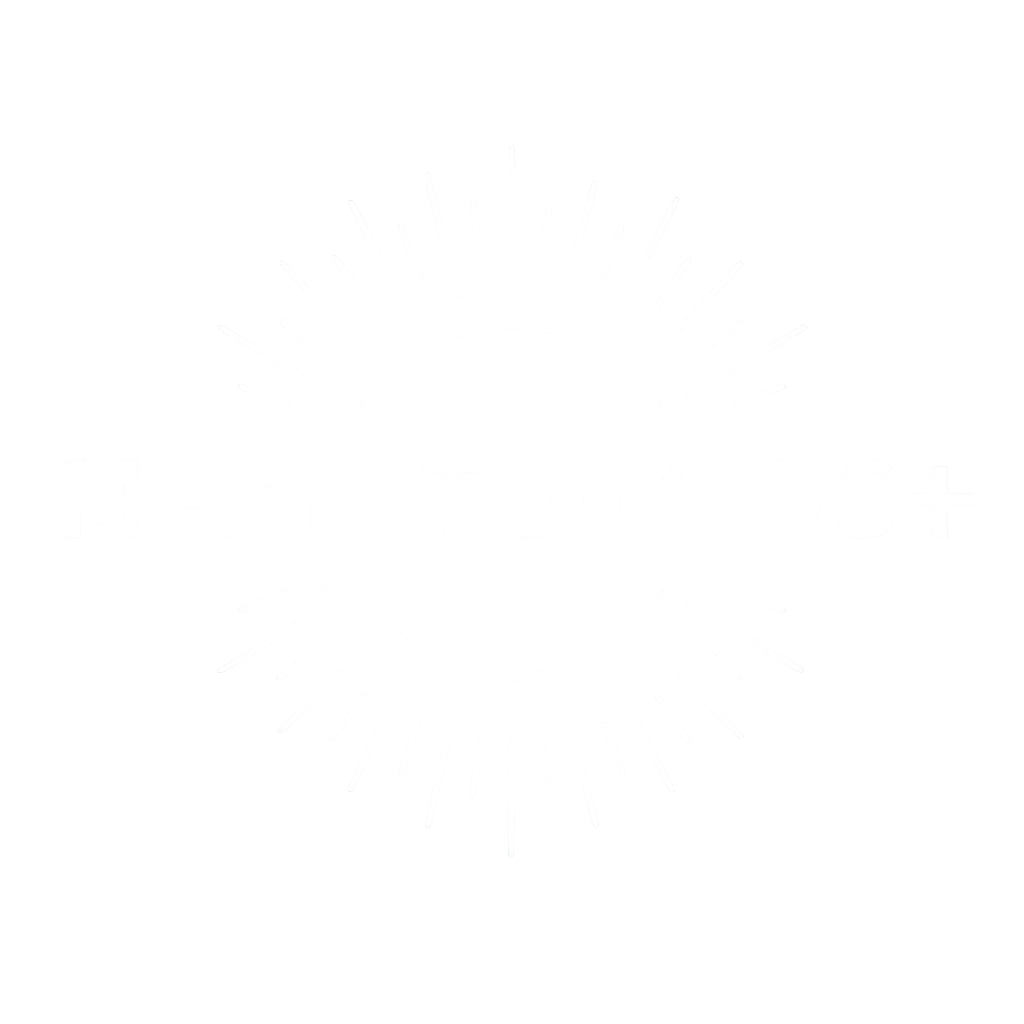










_白抜き-1024x576.png)