「この子、やる気がないんです」
「言わないとすぐダラけるし、集中力も続かない」
――これは保護者から本当によく聞く声です。
でも、ちょっと待ってください。
やる気って、本当に“本人の性格”や“努力不足”のせいなんでしょうか?
答えは、NO。
やる気は「才能」でも「気合」でもありません。
実はそこには、身体と脳のメカニズムが深く関係しているのです。
「やる気」は脳のある場所から生まれる

やる気を生み出すのは、脳の“側坐核(そくざかく)”という部分。
ここが活性化すると、「もっとやりたい!」という気持ちが湧いてきます。
この側坐核を働かせるカギとなるのが、ドーパミンという神経伝達物質。
ドーパミンは、
- ワクワクしたとき
- 目標が見えたとき
- 体を動かしたとき
に多く分泌されます。つまり、体を動かすことで脳が“やる気モード”になるというのは、科学的にも証明されていることなのです。
子どもの“やる気スイッチ”は「成功感覚」で入る
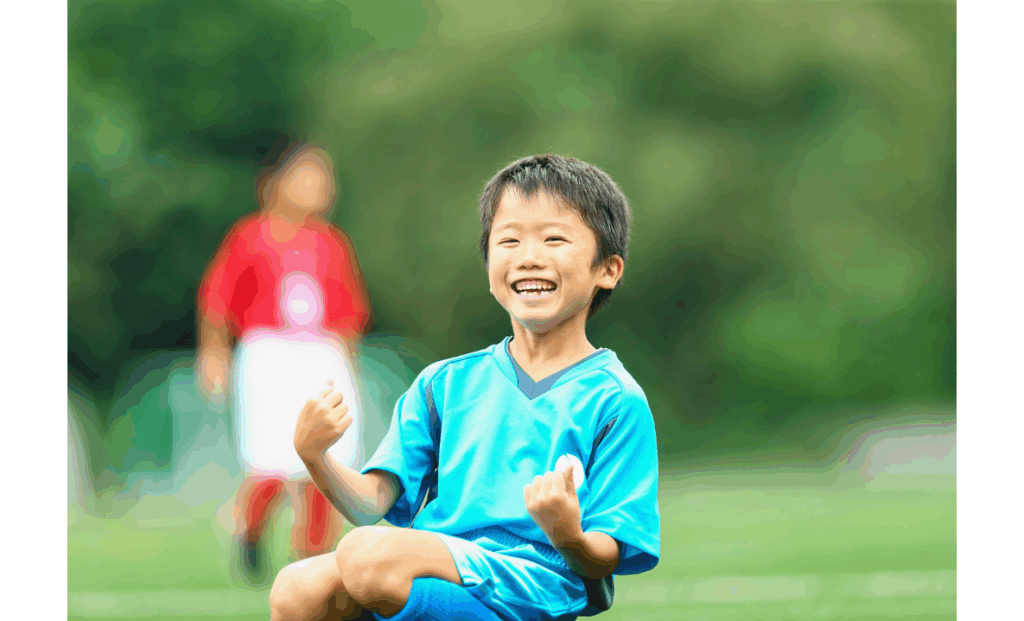
やる気を引き出すには、まず「小さな成功体験」が必要です。
たとえば、うまくいかないラダードリルに対して、
「どうしたらできそうか、一緒に考えてみよう」
「今のやり方、さっきより全然よくなってるよ!」
こうした声かけと共に、「自分でできた!」という実感が生まれると、脳はドーパミンを出します。
この“ちょっとできた感覚”が、やる気のスイッチになります。
逆に、「なんでできないの?」「ちゃんとやって!」は、脳のスイッチをバチッと切ってしまう言葉です。
“動かないからやる気が出ない”のではなく、“動いてないから出ない”

よくある誤解がこちら↓
「やる気が出たらやる」
実際のところは、やってみたらやる気が出るのが正解。
子どもはじっと座っているよりも、体を動かしたほうが、やる気も集中力も高まりやすいんです。
これは脳科学でも認知心理学でも一致している事実。
じつは、大人の「運動後にスッキリする」感覚も同じ仕組みです。
だから、
「勉強に集中してほしい」
「やる気が出てほしい」
そんなときこそ、体を動かす時間=“脳の準備体操”を入れてみてください。
本人が選べる環境が“モチベーション”をつくる

やる気には、もうひとつ重要な要素があります。
それが「自己決定感」です。
「今日はどっちのメニューをやってみたい?」
「どこまでできそう?」
「最後、自分でゴール決めてみる?」
このように“選ばせる”ことは、子どもの内側から湧いてくるやる気(=内発的動機づけ)を高めるポイントです。
やらされるとやる気が出ない。
自分で決めるとやりたくなる。
これは、子どもも大人も変わりませんよね。
「やる気がない子」なんていない。

子どもにやる気が見えないとき、それは「スイッチが入っていないだけ」です。
だから必要なのは、責めることではなく、スイッチを探してあげること。
- 小さなできたを一緒に見つけてあげる
- 成功を“見える言葉”でフィードバックしてあげる
- 本人の「やってみたい」を尊重する
こうした積み重ねで、子どもは自分でスイッチを押せるようになっていきます。
最後に:モチベーションは育てられる

「やる気スイッチが入らない」
そんなときは、“動き”を変えてみるのがいちばん早い方法です。
私たちのジムでも、最初は無表情だった子が、
少しずつ成功体験を重ねて、「もっとやっていい?」と前のめりになる瞬間があります。
その変化は、親御さんにとっても「えっ…うちの子、こんな表情するんだ」と驚くほど。
モチベーションは才能ではありません。
動き・声かけ・関わり方で、じわじわ育つ力です。


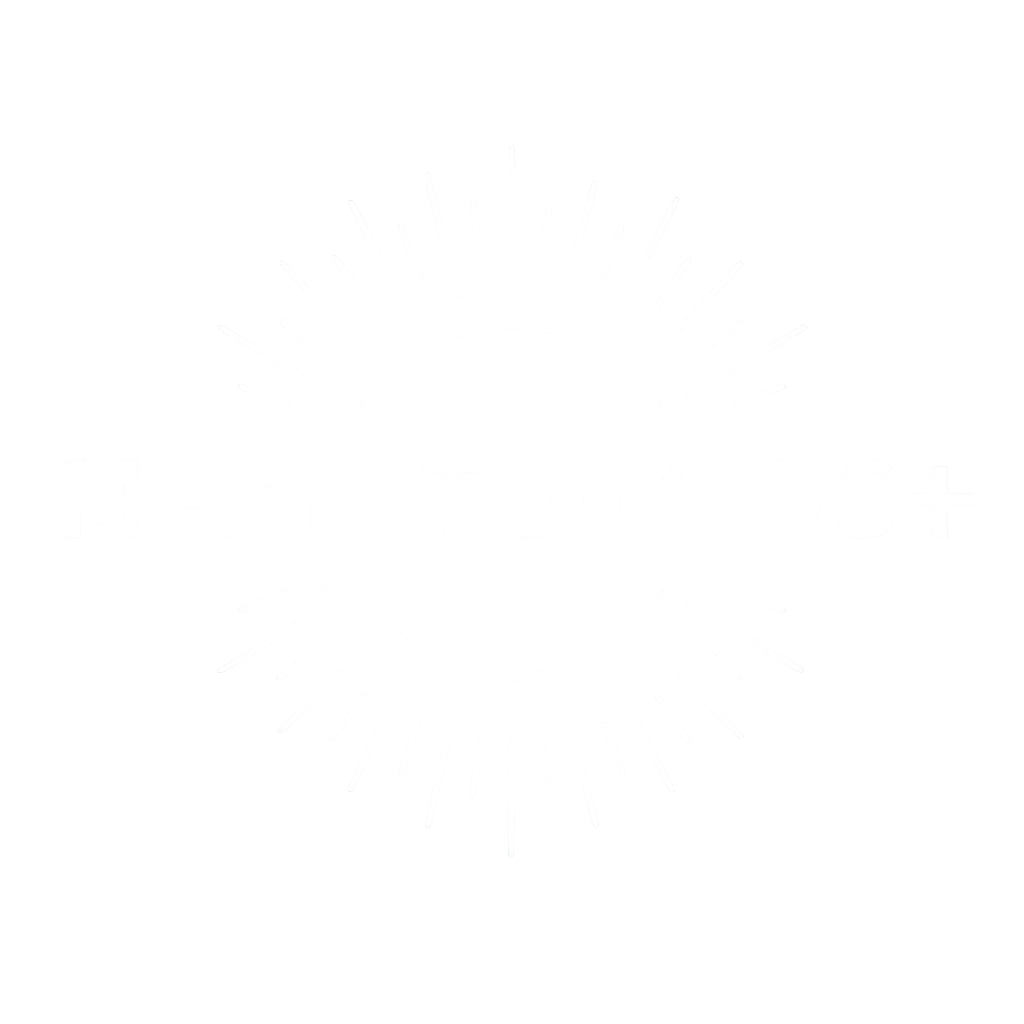










_白抜き-1024x576.png)