「うちの子、運動が苦手で…」
「体育の時間が憂うつみたい…」
そんな声、よく聞きます。
でも実は、“運動嫌い”は生まれつきじゃないことがほとんどなんです。
脳科学・発達心理学の視点から見ると、ちょっとした環境や経験の積み重ねで、運動に対する気持ちは大きく変わります。

1. 運動嫌いの根本原因は「できない記憶」
子どもが運動を嫌いになる一番の理由は、できなかった経験の蓄積です。
「ドッジボールで当てられた」「かけっこでいつもビリ」「縄跳びが飛べない」…
こうした経験が、脳に“運動=つらいこと”という記憶として刻まれてしまうんです。

2. “小さな成功体験”が脳を変える
脳は「できた!」という達成感を覚えると、ドーパミンが分泌されます。
これが次のチャレンジへの意欲を引き出す原動力になります。
つまり、運動嫌いを変えるには“小さな成功”を積み重ねることが最優先。
最初から大きな成果を求めるのではなく、
- 1回でも多く飛べた
- 今日は昨日より速く走れた
- 前よりボールを遠くに投げられた
…そんな小さな成長を一緒に喜んであげることが大切です。

3. 「競争」より「協力」
苦手な子にとって、“競争”はプレッシャーになりがちです。
そこで有効なのが、協力型の遊びや運動です。
例えばリレー形式でも「バトンをつなぐチーム感」を強調したり、
ペアでのキャッチボールや一緒にゴールを目指すゲームを取り入れると、
「みんなで楽しむ」感覚が芽生えて苦手意識が薄れます。

4. 運動を“勉強と同じく習慣化”する
勉強と同じで、運動も習慣にすると脳と体が慣れてくるものです。
週1回よりも、1日5分でも毎日のほうが効果的。
簡単なストレッチやジャンプ運動など、日常生活の中に取り入れやすい形から始めましょう。
まとめ
運動嫌いは才能の有無じゃなく、経験の積み重ねで変わります。
「できない」経験を「できた!」に変える小さなきっかけがあれば、
運動は子どもの一生の武器になります。


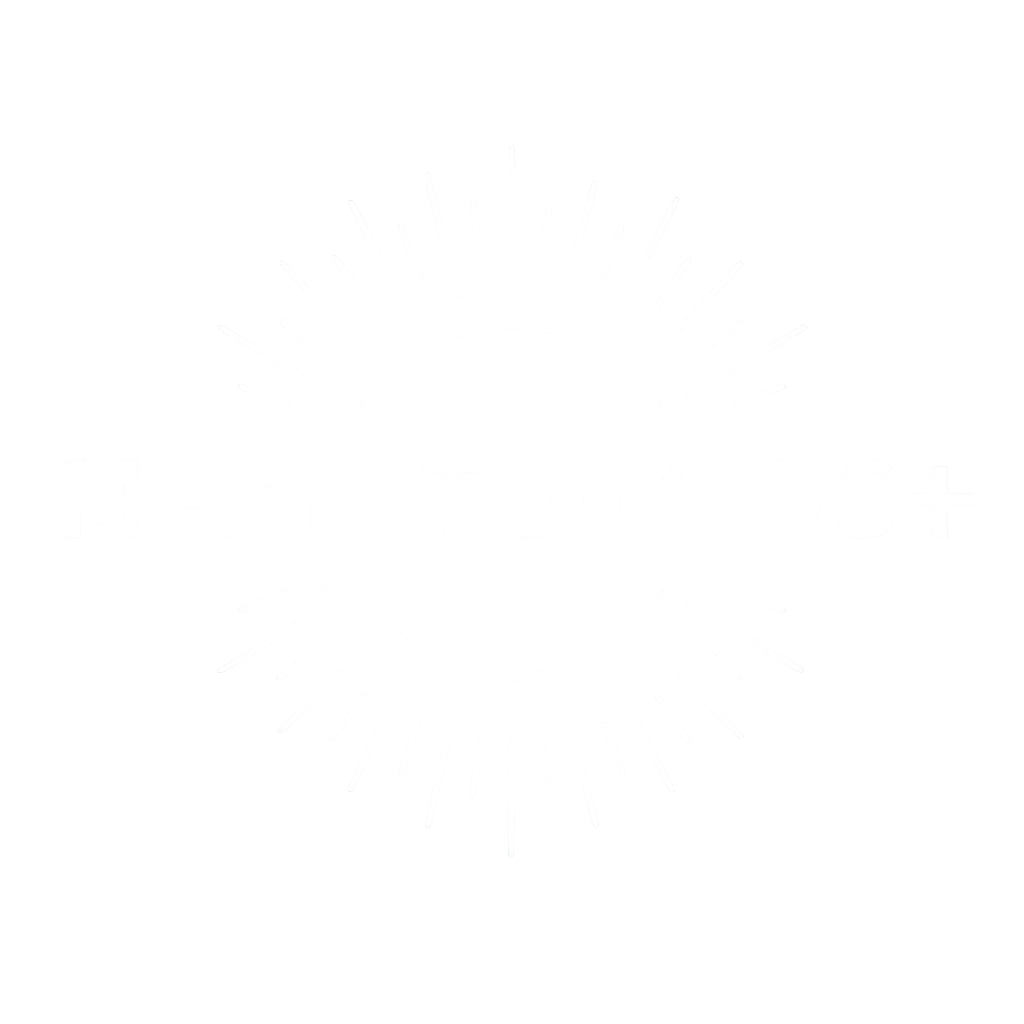








_白抜き-1024x576.png)